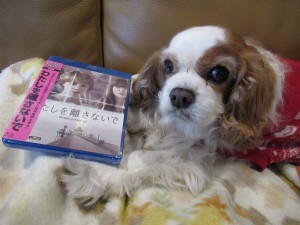カズオ・イシグロの『わたくしを離さないで』は、後でジワーとくる作品のような気がする。いろいろなことが、断片的に思い浮かぶ。
確か手塚治虫の漫画に、クローン人間が出てきたものがあったように思う(「火の鳥」か?)。そのクローン人間が感情を持ち、恋愛感情までもってしまった時、その後どうなるのであろうか。
酪農農家でニワトリや豚を飼い育て、それらに愛情を注いて愛おしいと感情移入してしまった時、そのニワトリや豚をと殺場に送る時は、どのような気持ちになるのであろうか。(それを思うと、動物を可愛がらない方がよい?)
(小学校のクラスで豚を飼い、それをと殺に送り出すということを子ども達にさせる実践があったが、それは残酷な実践だと思う)
幼年期、少年期を素晴らしい理想的環境のもとで育てられた子どもが、出て行く社会では過酷な運命や環境が待ち受けているとするとき、幼年期、少年期にその過酷さを教え、体験させていくべきなのか。
(もう少し具体的には)小学校で理想的な教育を行い、その子たちのその後入学する中学高校ではその対極の管理教育が行われ、また出ていく社会も過酷な現実が待っていて、その理想的な教育を受けた子どもたちが不適応を起こし不幸になるという場合、小学校の理想的な教育はよかったのかどうか。(あるいは小学校の時だけでも、いい思いをさせた方がいいのか)
この世に生まれてきた理由ははっきりしていて、その使命を果たした時命は果てる、普通の人と同じようでいて、かなり違う。普通の職業には就けず、カップルにはなれるが、結婚はできず子どもも産めない、寿命は普通の人の3分の1程度ーこの前提は揺らがず、その前提のなかで喜怒哀楽を感じる。とても哀しい存在。(普通の人も結局同じ?)
個人は社会の存続・発展の為に存在し、社会の中でのそれぞれの人の運命や役割はあらか決まっている、その役割が終えた時点でその人の寿命が来てこの世を去る、それを知っているのは神(=社会)のみで、個人はそれと知らず、自主的主体的に生きているようでいて、実は決められた運命にしたがって生きているだけである。
何も現実を知らずに過ごした幼少年期(モラトリアム期)やその場所や出来事が、切ないほど懐かしい。
―そんなことを、『わたくしを離さないで』は思わせる。