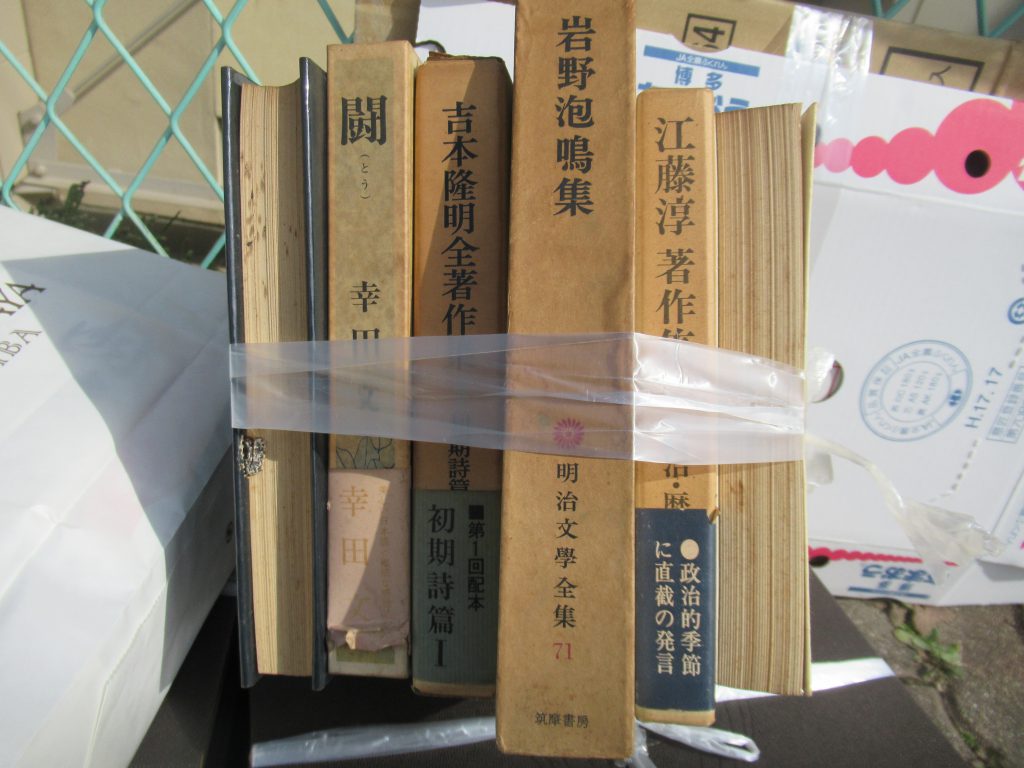主に教育現場の先生や教育委員会の人が読む情報誌(毎週2回発行)に、内外教育(時事通信社発行)がある。そこでどのようなことが今論じられているのを知りたくて、過去2年分くらいを拾い読みした。文部部科学省の各種委員会の報告、各都道府県教育委員会の動向、教育関係の調査データの紹介、外国の教育事情、教育関係の学会やシンポの報告、教科書の採択状況、教育関係の雑誌記事の紹介など、教育関係の政策から実践まで幅広く、事実に基づく記事が多く、参考になる。その情報誌の最初には、教育関係者の800字ほどのコラム(「ひとこと」)があり、文部科学省関係、マスコミ関係、大学役職者に混じって、知り合いの教育研究者が書いている(教育社会学専攻の人が多い)。その論から、最近の教育事情が窺い知れる。そのいくつかを抜き出してみよう(後に、元のものをコピーする)
〇「子どもたちは、直に恐竜の化石に接して、「おや、なぜ、すごい」を連発している。ここには何物にもとらわれない開かれたしなやかな感性がある。体験という学びの原点をそこにみた」(児邦邦宏「学びの原点」)
〇「私は学生に『1つのことを深く学んだら、そこから多様なものに拡大し別のことに応用したりすることができる』と言っている。ところが、どうやら最近の教員養成をめぐる議論は、真逆の方向に向かっているらしい。(それは)『人は教えたことだけしか学ばない』という決めつけである」(広田照幸「教員養成像の貧困」2017.6.6)
〇「高い目標が少数だけ簡潔に掲げてあるのであれば、それに向けて少しでも近づくための努力を教師はやれるかもしれない. 高くて広くて細かい目標は、教師を追いつめるだけ」(広田照幸「こんなの無理」2018.2.27)
〇「今回の学習指導要領は、学力の中核に『学びに向かう力・人間性』を据えた。その志を具体的にどのように実現するのか。それは、学校現場を担う先生方の双肩に懸かっている」(志水宏吉「新しい学習指導要領に寄せて」)
〇「学びにおいて個人作業は協同化されることによって最大の効果を発揮することができる。学びにおいては、いついかなるときも子どもを孤立させてはならない」(佐藤学「自力解決という異様な光景」2016.11.1)
〇「情報が氾濫している中で、それを選択する力はまさにこれからの社会を生きる力。無視する力は高度情報化社会においては生きる力の中核ともいえるであろう」(新井郁男「新しい時代の教育―善く生きる力」)
〇「教育において求められるエビデンスとは、目の前の授業が、その社会で求められる『教育的な営み』となっているかどうか、そしてそれが可能になる条件は何かに関する詳細な分析だ」(酒井朗「スモールデータの重要性」2018.10.19)
〇「大事なのは、一部の問題を、私たちみんなで考えていくという姿勢ではなかったのか」(内田良「ブラックは一部!の罪」2018.8.10)
〇「基礎は学校で学ぶ機会が公平にあるが、それ以外となると家庭で教育にかけたお金と時間の差が響く。しんどい環境の子どものハンディキャップを改善する役割を果たさねばならないのは、小中高の学校教育である」(氏岡真弓「思考力問う改革と格差」2018.1.30)
〇「社会は確実に分断されてきている。 多様な背景を持った人々が相互に理解し合い、共生していくためにはどうすればいいのか」(酒井朗「はじめて知りました」2017.12.15)
〇「日本社会は、業績主義の中で、失敗がもたらす絶望を緩和する文化的仕組みを組み備えた優しい社会だ。今回は運がなかった、チャンスに恵まれなかっただけだ、と自分を傷つけずにすむ思考様式に恵まれている」(耳塚寛明「運やチャンスと言える社会」)
〇「教育行政は国民のために行われるべきものであって、与党の政治家のためのものではない。政治と行政との間には距離や緊張感が必要だ」(広田照幸「しっかりしてくれ、文科省!」2018)
友人のU氏より下記のコメントをいただいた。
<各先生方のこれまでの論調を思いうかべながら興味深く拝見しました。ただ、どの論考にも、学校現場の授業が教科の縛り(依存)のなかで展開されることへのリアリティーを見出せない、というのが率直な感想です。言い換えれば、学習指導要領の総則の世界と学校の現場とのズレを前提に論じる視点を確認できません。その意味で、広田先生の「無責任な官僚と『有識者』の産物」という認識に半ば同意しますが・・・・他方で、指導要領の総則の冒頭には「児童の心身の発達の段階や特性および学校や地域の実態を十分考慮して」とあることとの矛盾にまで進まないことに、違和感(理解不足・考察の浅さ)を感じました。さらに現場の教師の教師が必要なのは学習指導要領ではなく教科単位の教科書とのリアリティーが生む学校教育の”ゆがみ”と重ねるフィクションとしての学習指導要領の大層な言語空間の機能を揶揄する知的遊戯にまで深めてほしいと思いました。私見ですが、既に学習指導要領は、多くの学校現場で、教育委員会も含めて、形骸化が進行しています。(私がこれまでの研究と教育で培ったのは)学習指導要領を利用して、今と未来を生きる子どもたちに、研究者として必要と判断する教育内容と方法を提示する(こと)、もう一つは、私が知る教師が実践できるかどうかというフィルターをかけることを忘れない、という教訓です。>