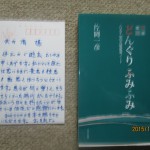同じ千葉の海でも、内房と外房ではかなり違う。内房は東京湾の中にあり、外房は太平洋に面している。
私は雄大で砂浜も水もきれいな外房が好きなのだが、内房の海を見たくなる時が、時たまある。
内房には、平凡な景色ばかりの千葉には珍しく、びっくりするほどきれいな景色のところがある。
それは富津から保田にかけての丘の上からの海の眺めである。対岸に三浦半島が見え、鏡のような静かできれいな海が広がって見える。東京湾を船が行き交い、天気がよければ、富士山もよく見える。
今日は、1年ぶりくらいに内房に車で出かけ(家から高速を使い1時間10分ほど)、その素晴らしい景色を満喫してきた。近くの漁民組合の食堂で食べた「マグロの荒煮」も美味しかった。
その後、房総半島の南の真ん中を横断し(東に1時間半)、水仙畑や千枚棚を見学しながら、外房に出て、きれいな海を眺め、帰宅した。
投稿者: takeuchi
テレビ視聴について
テレビを皆、どのくらいの時間見ているのであろうか。私の場合、テレビ視聴は無駄な時間と思い、ほとんど見ない。
私の青少年期、家にテレビが置かれるようになったのは中学の時である。したがって、日常的にテレビをみる習慣がついていない。
中高時代は受験勉強に忙しく、テレビを見る暇はなかった。高校時代に試験が終わり、時間ができた時は、テレビより映画を見に行った。大学時代そして現役で働いている時代も、テレビをのんびり見たという記憶がない。
また、家庭で私にリビングのテレビのチャンネル権がないので、好きな番組(映画が多い)を見ることができない(最近は、幼児向けの番組がついているので、それを見ることが多い)
それが、今日はたまたま、誰にも邪魔されず、1時間半ほどテレビを見ることができて、テレビもいい番組をやっているなと感心した。
ひとつは、NHKEテレ午後8時〜9時の「日曜美術館」(再)である。国吉康夫という明治生まれでアメリカで活躍し絶賛された画家の波乱に満ちた生涯とその絵が紹介されていた。美術にまったく無知の私でも、生きた時代と絵の内容の説明が明確で、引き込まれるようないい番組であった。氏の展覧会を見に行くたくなった(ワシントンで開かれている?)
もう一つは、放送大学の「教育社会学」第13回の岩井八郎・阪大教授の授業である。犯罪と社会の関係を扱った内容で、犯罪社会学の理論を平易に説明し、今の青少年の犯罪傾向とマスコミ報道とさらに世論の特徴をきわめて明確に、それでいていまの社会的風潮に対する鋭い批判を社会学的にさりげなく述べていた。格調高い講義だと感心した。到底私にはできない。教育社会学の講義全15回を聞きたくなった。
このように、テレビ番組も(馬鹿にせず、チャンネル権を奪い返し?)これから見ようと思った次第。
フォット・ジャーナリストー安田菜津紀さん
昔の「教え子」が有名になり、テレビなどに出ているのは、少しうれしい。
ただ、「教え子」と言っても、私のゼミ生ではなく(増渕ゼミ)、私の授業が必修で、授業に出て単位を修得したに過ぎないのだが、少しは私の教えたことが役立っているのであれば、うれしい。
今日(27日)の朝のTBS「サンデーモーニング」に、有名人に混じり、コメンターとして、控えめながら堂々といい意見を述べていた安田菜津紀さんがいた。
彼女は、上智大学の教育学科の2年生の時、後輩の男の子たち数人を引き連れてイランやサウジアラビヤに行く計画を立てていた。同行予定の男子学生のひとりの親から旅行を中止するように説得してほしいと学科に願いが出た。それで私が安田さんと、いろいろ話し合ったことがある。
大学の学生部に問い合わせたところ、たとえその地域に危険情報が流れていても、大学として渡航を禁止できないと言われた。学科に常時滞在先を連絡するように約束して、渡航を認めた。
結果的には、無事いい旅行だったようで、その後彼女は、アラブやアジアそして東北の子ども達の写真を多く撮り、フォット・ジャーナリストとして、活躍している。
そのサイトを見ると、世界の子ども達や東北のいい写真がたくさん掲載され、いいコメントが書いている。
飛び出すカード
昔のゼミ生から、素敵なカードを送っていただいた。写真のように「飛び出すカード」で、その精巧な作りには、びっくりする。
家にいる3歳の子も1目見て、「ワオ―」と,感嘆の声を上げた。
「カードもそうですが、『飛び出す絵本』は、男の子が喜ぶ飛行機や列車系など、すごくリアルで精巧にできたものがたくさんありますね。だいたい洋書ですが。子どもと一緒に本や文具を探すのも面白いです」というコメントもいただいている。「飛び出す絵本」も早速探してみよう。
さらに、このブログをみたMさんより、自分でいろいろ工夫して、機械のしくみを作り、知る本を贈って頂き、子どもは大喜び。
そして、アメリカの大学院に留学したことのある卒業生のI氏が、飛び出す絵本(動画)について、下記のような情報を送ってくれた。。
<飛び出す絵本はhttp://varadoga.blog136.fc2.com/blog-entry-67765.htmlの動画(31分以降。途中数回CM入りますが、すべて2分飛ばしで次へ移れます)でいろいろ勉強できますよ。※ 動画の近くに出て来る広告が邪魔ですが、×の部分をクリックするとすべて消せます。(私が留学した)イリノイ州立大はアメリカの児童文学研究の拠点のような大学でしたので、そちらの方面もそれなりに詳しくなりました。>
昔懐かしい人から便り(さく壁読書会の先輩)
昔の私の大学時代を思い出してみると、間違えて理系に入学してしまったこともあるが、3年次に進学した教育学部の授業も興味を惹くものでなかったし、入った大学のサークルも自分の得意な分野ではなく、悶々とした暗い日々を過ごしていたように思う。
そのような折、家の近くの市川市立図書館に、「さく壁読書会」という会が月に2回開かれているのを知り、ポスターを見て、それに参加するようになった。
参加した初回のテキストは、大江健三郎の『死者の奢り』だったように思う。毎回各自テーマの本を読んできて、自由に討議するような会であった。お蔭で、たくさんの小説を読んだ。この会は、200回以上続き、私も3年以上参加し、多くの友を得た。
その時中心になっていたのは、片岡一彦さんという中央法学部の4年生で、私より2歳上の人だった。その世代の文学好きの人たちが集まり、同人誌のようなものまで出していた。そこには、大江健三郎ばりの小説が何篇も掲載されていた
読書会やその後の喫茶店での話し合いは、私にとって新鮮なものであり、暗い大学生活に一条の光がさしているようなものあった。その先輩の片岡さんのアパートはうちに近いということもあり、よく家に来てくれて、いろいろな話を聞きことができた。母もその片岡さんのことはよく覚えていた。
その片岡さんより、今回母へのお悔やみの言葉と、片岡さんが書かれた素敵な本を贈っていただいた。片岡さんは若い頃に小説を書かれていただけあり、その文章に香りがあり、それに円熟さが加わり、味わいの深い内容になっている。
片岡さんのはがきと本を、仏壇の前に置き、亡き母にも報告した。母は、喜んでいることであろう。。