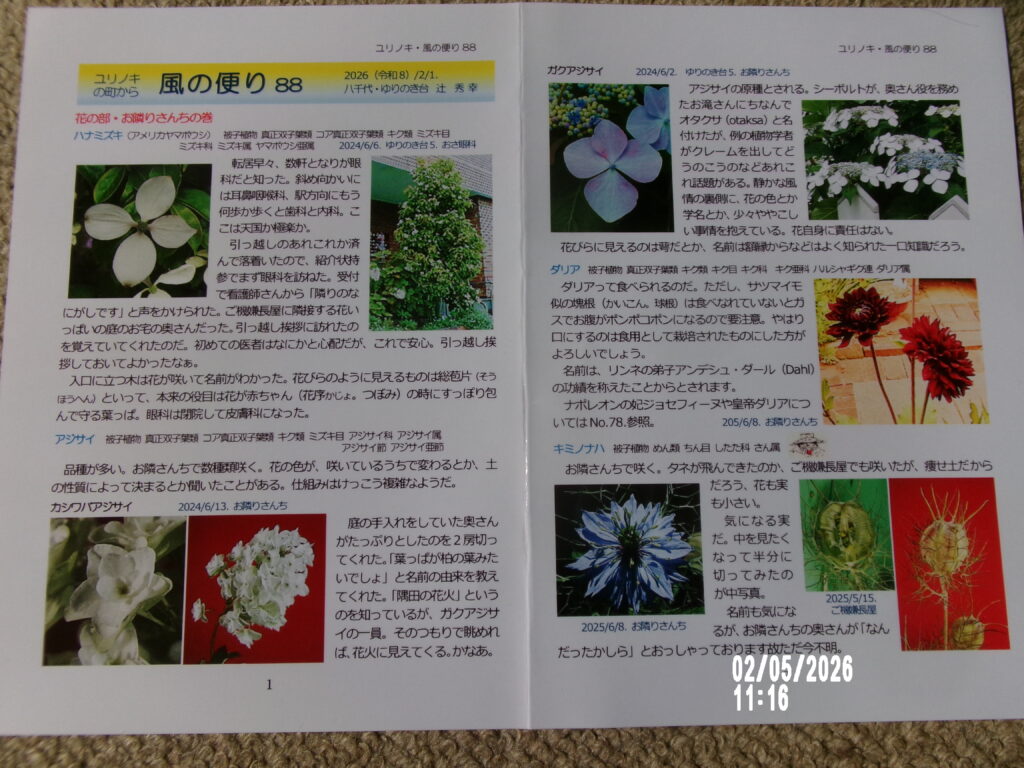作家は本が売れれば高い収入が得られるので、文筆の収入だけで食べていけるけれど、同じ文学者でも文芸評論家はそのようなことがなく、他の職業に就いて生活費を稼がねばならない。私の知っている限りで言えば、江藤淳は東京工業大学、石原千秋は早稲田大学、加藤典洋と高橋源一郎は明治学院に専任教員として勤めていた時がある。そこで、チャットGPTに 「他の例(人)があったら教えてほしい」(質問1)と、「大学化した文芸評論は文学にとって何を得て何を失ったのか,を教えて下さい(質問2)と尋ねた。その回答を転載する。回答に概ね納得した。(柄谷行人は「法政大学・近畿大学・イエール大学などで教鞭」だと思うが)
質問1の回答;代表的な例を挙げます。戦後〜高度成長期世代+小林秀雄( 大学教員ではありませんが、例外的に「評論一本」で成立した希少な存在、吉本隆明(東京理科大非常勤などはあるが、長くは在野の思想家・評論家)、蓮實重彦(東京大学教授(仏文学・表象文化論)、柄谷行人(近畿大学・コロンビア大学などで教鞭)、渡部直己(早稲田大学教授)、三浦雅士早稲田大学教授)、1970–90年代以降;松浦寿輝(東京大学教授(比較文学)、沼野充義(東京大学教授)、千葉雅也(立命館大学教授)、小森陽一(東京大学教授)、山城むつみ(慶應義塾大学教授)/この系譜から分かるのは、「文芸評論家=大学教員」ではなく、正確には「研究と評論を往還できる人が大学にポストを得やすかった」という構造です。/ 構造的まとめ(重要)ご質問の背後にある核心は、次の点にあると思います。1. 作家と評論家の「市場価値」の非対称性-小説・エッセイ → 読者市場がある. .文芸評論 → 市場が小さい/専門的。2. 戦後日本における「大学=評論のインフラ」安定収入(給与)図書館・研究時間、学会・雑誌との接続。 その結果、文芸評論は「半ば学問化」し、大学に居場所を持たない評論家は減少しました。3. 例外の意味、小林秀雄・吉本隆明の「在野性」は、今日では再現困難。>
質問2の回答;Ⅰ.得たもの(獲得) ① 批評の「持続可能性」最大の獲得は、時間と生活の安定です。定職による安定収入、研究時間の確保、図書館・データベースへの恒常的アクセス。これにより、長期的な作家研究、複数作品を横断する体系的批評、即時的評価ではない「遅れて効く」批評が可能になりました。 江藤淳・蓮實重彦・柄谷行人以降の批評は、「一冊で終わらない批評」を成立させています。② 批評の理論化・方法化。大学という場は、批評を「技法」に押し上げました。構造主義・記号論、精神分析、ポストコロニアル理論、ジェンダー研究・カルチュラル・スタディーズ。これにより、「印象批評」からの脱却、恣意性の相対化、再現可能な読解モデルが生まれました。 文芸評論は「うまく書ける人の芸」から「共有可能な知」へと変質しました。③ 文学の国際的接続大学化は、日本文学を世界語と接続しました。翻訳研究、比較文学、世界文学の文脈化。結果として、日本文学が「国内趣味」から脱却。村上春樹・大江健三郎などの国際評価の下支え。 批評は、文学の通訳者になりました。④ 文学の保存装置としての機能大学は「アーカイブ」として働きました。忘れられた作家の再評価。マイナー文学・女性文学・地方文学の掘り起こし戦争文学・被差別表現の検証。 市場が忘れても、大学化した批評は「忘れない装置」になった。/.失ったもの(喪失).① 読者との緊張関係..最も大きな喪失です。読者が「専門家」に限定される。文体が内輪化・専門用語化,雑誌的公共圏の縮小..かつての小林秀雄を読むこと=文学を読むことという等式は成立しなくなりました。 批評は文学の「内側」に閉じこもった。② 評論の〈賭け〉の消失。在野批評にあった書くことで生活も思想も賭けるという緊張。原稿が売れなければ生活できない。誤れば即座に信用を失う。読者の反応が直に返る。大学化はこれを緩和しました。 批評は「安全な言説」になったとも言える。③ 文体の衰弱。大学論文的文体の拡張は、説明的、注釈過多、断言を避ける傾向を生みました。結果として、文学を論じる言葉が文学的でなくなる。批評文そのものが読まれなくなる。「批評が文学である」という感覚が後退。④ 文学と社会の距離の拡大かつての文芸評論は、政治、戦争、労働、倫理と直結していました。大学化以降、社会批評は社会学・思想史へ分散。文芸評論は「作品内部」へ収斂。 文学が社会の痛点を代弁する役割を部分的に失いました。Ⅲ.総合的評価:得失はトレードオフか?重要なのは、これは単なる「堕落」ではなく、制度的選択の結果だという点です。在野性 → 強度はあるが持続しない。大学化 → 持続するが強度が弱まる。文学は、市場(作家)。大学(評論)。メディア(読者)という三者の緊張関係の中で生きています。問題は「大学化」そのものではなく、他の回路が痩せてしまったことです。Ⅳ.これからの可能性(補足)近年、次の兆しもあります。書籍外(ウェブ・講演・ポッドキャスト)での批評。文学研究者によるエッセイ的回帰。作家自身が批評を書く再接続これは、大学化によって失われた「公共性」を、別ルートで回復しようとする動きとも読めます。